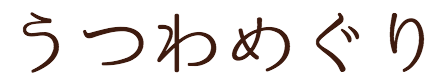BLOG
2022/07/14 15:20
高取焼宗家

黒田藩御用窯・唯一の直系窯であり、
420年を超える歴史を迎える高取焼宗家。
伝承者のみにしかわからない釉薬の製法と
こだわりの秘法は長きに渡って守り続けられている窯元です。
陶器でありながら磁器のような薄さと軽さ、
精密な工程、華麗な釉薬、
きめ細かく繊細な土質が高取焼の特徴です
そして、
現在も長石や唐土を唐臼で搗き(つき)
登り窯や単窯によって薪で焼成された器は、
伝統技法による味わいがあります。
<とても薄い作りに驚いた作陶の様子>


現在も、遠州のお家元に直接指導をいただきながら作陶されている高取焼宗家。
茶道の「おもてなしの心」を受け継いだうつわは
「綺麗さび」と表現されていて、
手にした時に、口をつけるたびに、
時間をかけて作られた
特別なうつわであることを感じることができます。
<薄造りを叶えるための土づくり>
サラサラの砂になるまで1ヶ月もかけて唐臼を使って搗いていきます。
(宗家さんの母屋の後ろには川が流れていて、敷地内にこの唐臼があります。
耳を澄ますと、ギーゴットンの音が聞こえてきます)

サラサラになった土は、水に溶かしてざるで濾していきます。2~3ヶ月かけてできた泥水をポンプで吸い上げ、
板状の粘土を作り、土練機によって真空をかけて筒状にした土を、
さらに数ヶ月間寝かせ、出来上がります。

きめ細かな陶土を作るところから、手間と時間を惜しまない、
このこだわりが、器に深い味わいを生み出しています。
<釉薬>
釉薬は、自然界から得られる、
「藁灰」「木灰」「サビ」「長石」
の4種類を使って、代々、高取焼当主にのみ伝えられる秘伝書により調合されます。
↓こちらは、高取焼七色釉薬のうちの3つが掛けわけされた器。(窯に入る直前のものを写真に撮らせていただきました)

同じ釉薬で仕上げた器でも、季節によっても、火の通り道によっても、
違った表情を生み出し、
また、釉薬が交わってできる模様は、なんとも言えない神秘的な雰囲気です。

以前、単窯に火が入るところも見学させていただきました。

この長い長い工程を経て、窯に並べられた作品たちが、無事に焼きあがりますように、、、!
遠州に好まれ、茶陶として有名な高取焼宗家の展示場には、
茶器や酒器を中心に展示をされてありますが、
奥様の七絵さん、息子さんの春慶さんが作り出される、
「現代の食卓にも、高取焼を楽しんでもらいたい」というコンセプトの
素敵な日常使いの器の数々は、
優しいデザインだったり、 使い勝手のいいものだったり、
使ってみたい✨ と思うものばかり。

食卓に、非日常な日常を届けてくれる器


ぜひ、
日々の暮らしの中で、ちょっと贅沢な味わいをお楽しみください。
<おすすめの器のご紹介>
百光(びゃっこう)シリーズ

春慶さんによって新しく調合された釉薬、百光釉✨
渋く、金色のように華やかさがあるシリーズは、酒器だけでなく、お皿、カップ、箸置きでも楽しめます。
この釉薬のわくわくするところは、
水やお酒を注いで中を覗くと、さらに煌めいて見えるところです。
家での晩酌が楽しくなる逸品です。
ハートの器

コロンと可愛い形をしたハートの器。
手のひらの中にすっぽり収まるこの器は、お猪口としても、副菜を盛り付ける小鉢としても、
そして、麺つゆを入れたり、ドレッシングを入れたりして、一人分づつ盛り付けるのにも、
とっても便利な器です。
そしてなんといってもハートフルなこの形。
目からも愛情を感じられる器は、食卓がほんわか柔らかい雰囲気に♪
丸マグカップ

親近感が湧く、ぽってりとした可愛い形で、
窯元でもずっと人気の丸マグカップ✨
下の方についた取手が持ちやすく、熱と香りを楽しめる形状です。
そして、どの陶器にも共通する飲み口の薄さ✨
その、口に当たる時の心地よさは、お猪口を口につけた時の感動と同じでした。
同じ形状のフリーカップ もあります♪焼酎やアイスコーヒーにもぴったりの器です。
<追記>
令和5年梅雨前線豪雨により、高取焼宗家様も、唐臼や土砂崩れなどの被害に遭われました。
1日も早い復興と、この歴史を繋ぐ陶器作りがこれからも受け継がれていくことを願っています。
高取焼宗家さんがチャレンジされたクラウドファンデイングにも当時の詳しい様子が書かれていますので、
どうぞこちらからご覧ください。
↓
https://rescuex.jp/project/87320
次の窯元へ行く→(早川窯元)
MAIL MAGAZINE
お得なクーポン、入荷案内、イベントのお知らせなどを、いち早くお知らせいたします